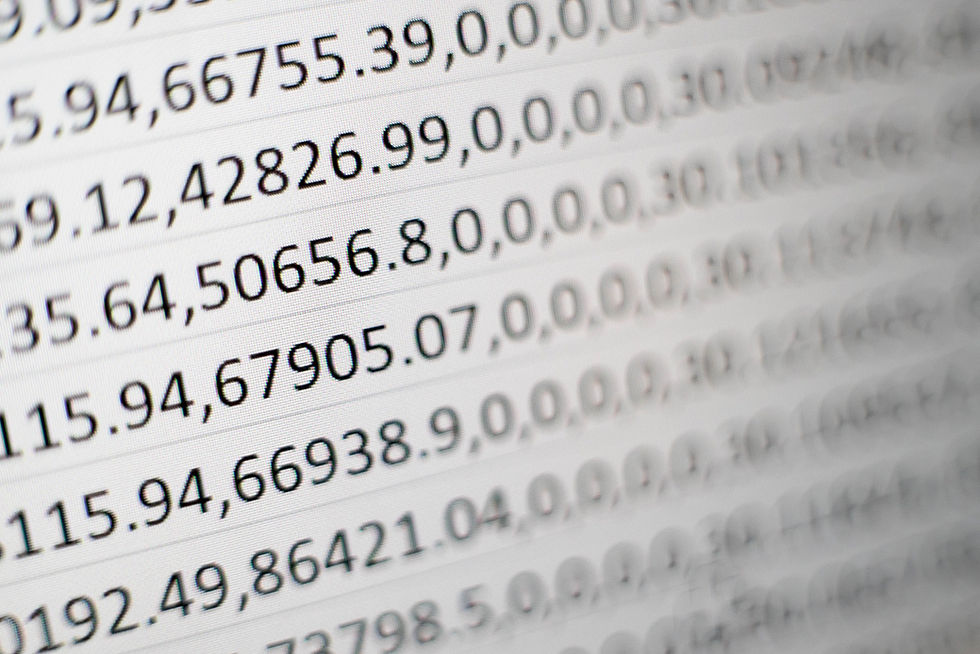
2025年11月5日
原価/販管費コントロールを中心に
要旨(Abstract)
営業代行事業は、これまで「人手架電→アポ取得→商談送り」モデルが中心であったが、近年、生成AI・音声応答AI・自動架電エージェントの導入により、「営業支援の原価・販管費をAIで制御する」新モデルへと転換しつつある。
本稿では、特に「架電業務」が営業支援の原価比率で最大を占めるという前提のもと、AIによる業務効率化・コスト削減・成果報酬型へのシフトがもたらす市��場変化を、定量データ・事例を交えて論じる。
例として、AI架電システムを導入した企業において「AIを活用して原価・販管費をコントロールする取り組みを行いました。我々は、特に架電業務が営業支援の原価として最も大きい比率を占めています。」という社内コメントを元に分析を付加した。
※https://www.mag2.com/p/money/1667204/amp
1. 市場の現状

グローバル営業代行市場規模は、2024年に約USD 30.9億、2033年にUSD 44.9億(CAGR約4.2%)と推定される。
日本におけるBPO市場も増加傾向にあり、営業代行サービスもその拡大の中に位置づけられている。
架電・インサイドセールス・アウトバウンドコール等、営業支援における「架電業務」が人件費・時間コスト・非効率ロスの3重構造として原価・販管費に大きな影響を与えている。
2. AI導入による原価・販管費コントロールの意義
上記の社内コメントに依れば:
“AIを活用して原価・販管費をコントロールする取り組みを行いました。我々は、特に架電業務が営業支援の原価として最も大きい比率を占めています。”
というように、営業アウトソーシングモデルにおいて「架電=原価・販管費の主戦場」という認識がある。
AI導入により、以下のような原価/販管費の削減効果が期待される:
人件費の削減(有人架電人数・時間の縮少)
架電回数の最適化・無駄削減(AIによる高速・大量架電)
教育・トレーニングコスト低減(AIスクリプト化・品質均一化)
ロス時間(不在・折り返し・手動転記)削減
3. 事例:AI架電の導入効果(仮定分析)

AI架電では例えば、「1コールあたり約 ¥15/コール〜」などの価格設定が提示されており、従来の手動架電と比較してコスト低減余地が大きい。
PITK - AIテレアポとWEB開発ならお任せください!+2PITK - AIテレアポとWEB開発ならお任せください!+2
本稿は以下の仮定モデルを置く:
架電業務コスト(人件+時間+付随経費)が営業支援原価の 40% を占める。
AI導入により架電コストが 30%削減。
削減分の一部(例えば60%)が販管費軽減・利益改善に直結。
この場合、原価・販管費合計を10とすれば、架電比率4→コスト削減30%=1.2 の削減。販管費軽減分0.72が利益改善に寄与というモデルになる。
さらに、AI活用チームの増収優位データ(83% vs 66%)などと合わせて考えると、導入先企業では粗利益率+5-8pt改善という仮�説も成立しうる。
4. 今後の変化予測(~2030年)

4.1 成果報酬モデルへのシフト
架電コストの削減が進むことで、従来「人月+成果コミッション型」から「成果単価+インセンティブ型」契約が増加。特に成果を明確に測定できる環境では、売上に対してロイヤリティ・成功報酬が上がる。
4.2 AI運用・設計の付加価値化
営業代行会社は、「AIを使って原価・販管費をコントロールできる」ことを競争優位に変える。架電業務のAI化を単なる効率化ではなく「コスト構造変革」として売りに出す。
4.3 内製化と外部伴走のハイブリッド化
クライアント企業がAI架電を内製化・部分内製化する動きもあるが、多くは「設計・運用・改善」を代行会社が担う伴走型モデルが主流となる。
4.4 日本市場特有の展開
日本では中小企業のAI活用率が低く、営業代行会社が「AI導入+原価削減+成果報酬型」モデルを提案することで、営業支援市場の再評価・拡大が期待される。
4.5 戦略示唆(営業代行会社/クライアント企業双方)
営業代行会社向け:提案段階から「AIによる架電コストモデル」「原価・販管費削減インパクト」を数値化(例:1コール¥15/旧体制¥30、年間架電数10万)して提示すること。
クライアント向け:成果報酬型契約導入と併せて、「架電原価をAIで制御できる代理店」の選定を優先すべき。
KPI整備:架電コスト/コール、アポ転換率、1アポあたりコスト、販管費削減�額、粗利率改善幅などをダッシュボード化。
5. リスク・限界
AI架電が「架電数を減らすコスト削減」方向だけで終わると、質低下・反応率低下リスクあり。
架電という原価構造に偏ったモデルだが、商談化・受注化に至る上流プロセスの質的改善も並行が必要。
日本独自の通話文化・顧客反応などでAI架電の受容性に地域差あり。
結論
営業代行市場では、「架電業務」という原価・販管費の大きな構成要素を、AIによってコントロール可能にした点が構造変化の鍵となる。
架電コストを削減できることで、営業代行会社は成果報酬型モデルを強化し、クライアント企業もコスト構造改善を享受できる。
今後、AI活用と原価・販管費の制御をセットに提案できる代行事業者が、市場の中で有利に立つと予測される。